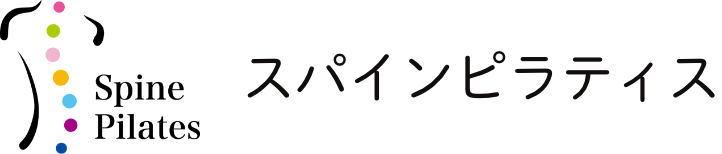お知らせ
【活動報告】Yuheiインストラクターがパルクールの大会に出場してきました!
2025.10.10
こんにちは。インストラクターのYuheiです。
9月末に人生初のパルクールのスピードランと呼ばれる競技に参加してきました。
聞き馴染みのない方もいらっしゃると思うので、パルクールの概要と運動の観点からピラティスとの対比、そして最後に実際に私がパルクールをしている動画もありますので、ぜひ最後までお読みください。
パルクールとは?
パルクールは、街中や自然の中にある障害物を利用して、走る・跳ぶ・登る・渡るといった動きを組み合わせながら効率的に移動する訓練法です。
フランス発祥で、「移動術」とも呼ばれることがあります。特別な道具や器具は必要なく、自分の身体ひとつで行えるのが特徴です。
昨今では、パルクールの競技化が進み、そのうちの1つである「スピードラン」は、スタートからゴールまでいかに早くたどり着くかというタイムを競う競技となります。
内的焦点と外的焦点
ここからは私自身がパルクールを実践し始めた経緯、個人的にお客さまにも取り入れていただきたいと思っている理由をお話しします。
ピラティスを利用される方は様々な目的を持っていますが、ざっくりと共通しているのは「日常生活の質を上げたい」ことだと思います。
そうなった時に、ピラティスだけでは補いきれない部分があります。それが見出しにある「内的焦点と外的焦点」という観点です。
内的焦点とは、身体の内側に意識を向けながら運動をすることで、ピラティスやヨガなどのボディワークが得意とする部分です。
筋肉の収縮感、関節の位置や動きといった感覚に目を向けることは自己の理解を高めていくプロセスとなります。
運動初心者や慢性痛を抱えている方は、自身の身体の感覚を正確に理解できていないことがあるため、このプロセスが大切になります。
しかし、意識が内側に向き過ぎると動作の連動性や出力が落ちたり、脳のリソースを使い過ぎることがあります。
例としては、考えすぎて歩き方がぎこちなくなったり、動作中に話を聞き逃すなどがあります。
対して、外的焦点は、身体の外側に意識を向けながら運動することで、パルクールなどの障害物を利用した運動が得意とする部分です。
障害物の高さ、距離感、地面の環境を理解し、環境に自分を適応させていくプロセスになります。
運動の初期に行ってしまうとかえって混乱を招く恐れがありますが、自身の身体の理解が追い付いてきたときには動作の連動性、出力の向上が期待でき、脳のリソースを他に使うことができます。
「いや、私はパルクールしないよ…」と思った方もいるかもしれませんが、「洗濯物を干す」「水たまりを避けて歩く」「自転車に乗る」といった日常生活全般も私たちは外的焦点で動いています。
したがって、「生活の質を上げたい」となったときに、この外的焦点で運動していくことが最終的には目指すべき運動スタイルだと思っています。
ここまでをまとめると、
内的焦点:ピラティスやヨガ
・身体の内側に意識を向けて動く
・自身の身体の理解に有効(運動の初期)
・連動性、出力の低下や必要以上に脳のリソースを使う
外的焦点:パルクールや日常生活
・身体の外側に意識を向けて動く
・連動性や出力の向上や脳のリソースを他に使える(運動の中期から後期)
・運動の初期には混乱を招くこともある
ピラティスとの相互補完
先ほどもお伝えした通り、ピラティスは自身の内側に意識を向けるインターナルフォーカスに非常に向いています。
ですので、序盤はピラティスを活用して自身の身体の理解に努めていくことが運動学習において有効と考えます。
そこからある程度、身体の理解ができてきたら意識を外に向けた運動にチャレンジしていきます。
ここで例を1つご紹介します。
【上肢プッシュ動作に対するインターナルフォーカスとエクスターナルフォーカス】
直立二足歩行で生活する人間にとって、手で体重を支える、手で押すという動作は少し疎遠になりがちですが、姿勢機能、呼吸機能の観点からこの「押す」という動作は非常に大切になります。
理由に関しては割愛させていただきますが、この「押す」という動作に対してのエクササイズフローをご紹介します。
1,ピラティスによるインターナルフォーカス
チェアと呼ばれるマシンを使用します。スプリングのかかったペダルを手で押します。この時に「腹筋に力が入る感覚」「背中が丸くなる感覚」「肩甲骨が外側に移動している感覚」などに意識を向けて、「押す」動作で起こる感覚を拾っていきます。
2,マットエクササイズによるエクスターナルフォーカスに向けた準備
四つ這い姿勢から壁に頭をつけるように動きます。身体が前に進むにつれて手に荷重がかかるので、先ほどのエクササイズに近い感覚で動いていきます。「頭がつく=手で押せた」という結び付けを深めていきます。
3,パルクールによるエクスターナルフォーカス
最後に障害物を利用して押す動作を身体に馴染ませていきます。ジャンプも利用しながら障害物を飛び越えていきます。ここでは、「飛び越えた=手で押せた」ということになるので、運動する本人としても結果の良し悪しが分かりやすいです。
まとめ
・日常生活の向上には最終的に意識を外に向けた中で運動する必要がある。
・運動初期は身体の内側に意識を向けて動き、中期から後期にかけて身体の外側に向けた運動も取り入れる
ここまで、読んでいただきありがとうございました。最後に私が動いている動画を載せますのでどうぞご覧ください。